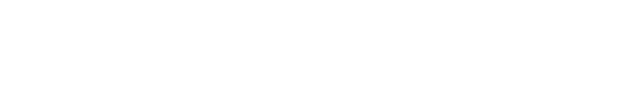不眠症について
はじめに
眠れない(不眠)は、皆さんの生活の質を落とすだけでなく、健康をそこねることにもなります。皆さんも、子供のころは「布団に入って、目が覚めたら朝(場合によっては昼)」という日の連続だったと思います。しかし、歳とともに、布団に入ってもなかなか寝付けない(入眠障害)、夜中にたびたび目が覚めてしまう(中途覚醒)、朝早く目が覚めてしまう(早朝覚醒)、しっかり寝た気がしない(熟眠障害)などの症状が出てきます。このような、眠れないつらさは、本人にしかわからないものです。それに加え、不眠は、日中のだるさや集中力の低下など、からだの不調も生じることがあります。
ツノクリでは、皆さんが、元気で幸せな生活を送るために、しっかりと眠ることが大切だと思っています。もちろん、しっかり眠るには、まずは生活リズムを整えることが大切です。しかし、それでもしっかり眠れなければ、睡眠薬と呼ばれるお薬を飲むことをお勧めすることもあります。皆さんにとって大切なことは、お薬を飲むかどうかではなく、元気で幸せな生活を送ることだと思っています。また、眠るためにお酒を飲むような方には、お酒を中止して、寝る前にお薬を飲むことが望ましいと考えています。さらに、最近のお薬の中には、今までのお薬と比べて、ふらつきなどの副作用が少なく、お薬の中断がしやすくなっているものもあります。そのため、昔から飲み続けているお薬の変更を提案することもあります。
ツノクリでは、眠れない方に、できるだけしっかり、かつ、できるだけ安全に眠れるようにお手伝いします。もちろん、ツノクリは、不眠専門のクリニックではありません。ご希望があれば、精神科やメンタルクリニックなど不眠を専門とするクリニックを紹介します。
インターネット上には、多くの不眠治療専門クリニックの情報があふれていますが、個人的には「MSD製薬 快眠ジャパン」のホームページが素晴らしいと思います。参考にしてみて下さい。
目 次
Q1.不眠症とは何ですか?
Q2.一晩で眠る時間はどのくらいが良いですか?
Q3.不眠症にはどのような種類がありますか?
Q4.不眠症にはどのような原因がありますか?
Q5.ストレスを除くと不眠症は良くなりますか?
Q6.不規則な生活リズムを整えれば不眠症は良くなりますか?
Q7.前立腺肥大症を治療すると不眠症は良くなりますか?
Q8.睡眠時無呼吸症候群を治療すると不眠症は良くなりますか?
Q9.レストレスレッグ症候群(むずむず脚症候群)とはどのような病気ですか?
Q10.お酒と睡眠薬を一緒に飲んでも良いですか?
Q11.睡眠薬を飲みたくないのでお酒で寝ても大丈夫ですか?
Q12.睡眠薬の中でも望ましい睡眠薬はありますか?
Q1.不眠症とは何ですか?
しっかりと眠れない夜が1か月以上続き、充実した生活を送れない状態です。
皆さんも、子供のころ、こころとからだの緊張により、試験や旅行の前に、なかなか寝付けない夜を経験したことがあるはずです。このような不眠は、当日もしくは数日で改善し、不眠症と呼びません。しかし、はっきりとした理由がなく、しっかりと眠ることができず、こころとからだに不調をきたすことがあります。さらに、そのような不眠と不調が1か月以上続くと、不眠症と診断されます。また、歳をとると、睡眠のリズムが変化しますが(多くは中途覚醒と早朝覚醒)、このような変化は不眠症とは異なります。もちろん、若いころに比べればしっかり眠れない不満はありますが、眠れないために日中の生活に支障をきたさなければ、積極的な治療の対象にはなりません。
Q2.一晩に眠る時間はどのくらいが良いですか?
理想的な眠る時間は、ひとりひとり違います。
一般的に、年齢によって変わりますが、成人で7~9時間ぐらいと考えられています。一晩で眠る時間は、年齢とともに減り、成人では約7~9時間で一定になります。また、65歳を越えると徐々に増え、75歳を越えると約8~10時間となり、途中で起きたり(中途覚醒)、朝早く目が覚めたり(早朝覚醒)、昼間に居眠りすることが増えてきます。ただし、眠る時間はひとりひとり違いますので、眠る時間に、あまりこだわらなくて構いません。
Q3.不眠症にはどのような種類がありますか?
不眠症には、以下の4種類あります。
- 入眠障害/にゅうみんしょうがい:なかなか眠ることができない
- 中途覚醒/ちゅうとかくせい :夜中にたびたび目が覚めてしまう
- 早朝覚醒/そうちょうかくせい:朝早くに目が覚めてしまう
- 熟眠障害/じゅくみんしょうがい:眠ったのにしっかり寝た気がしない
それぞれの種類によって、飲むお薬が違いますので、不眠症の種類を確認することはとても大切です。
Q4.不眠症にはどのような原因がありますか?
不眠症には、いくつかの原因が複雑に絡み合っています。
何らかの原因があって不眠症になっているのであれば、原因となる状態や病気の改善が大切になります。以下に、不眠症の原因になりやすい状態や病気には、ストレス、不規則な生活リズム、前立腺肥大症(→Q7)、睡眠時無呼吸症候群(→Q8)、うつ病、ムズムズ脚症候群(→Q9)、心不全(→「心不全について})、気管支喘息の発作(→「気管支喘息について」)などがあります。
Q5.ストレスを除くと不眠症は良くなりますか?
はい、治せる場合があります。ただ、ストレスを無くすのはとても難しいのも事実です。
日常生活でのさまざまなことがストレスになり、不眠症を引き起こします。取り除ければ取り除きたいですが、どんな人にも悩みやストレスはあります。ヒトは悩みと共に生きていますので、全てを取り除くことはできません。
Q6.不規則な生活リズムを整えれば不眠症は良くなりますか?
はい、なかでも入眠障害が良くなる場合があります。
まず、朝はできる限り同じくらいの時刻に起きます。日中は、運動を含めた活発な活動を行い、昼寝をしても15分前後にしましょう。夕食後は、寝るための準備と考えて、カフェインを控えて、遅くまでスマートフォンやテレビを見たりするのは控えましょう。寝る時刻や眠る時間は、人それぞれ異なりますので、眠くなったら寝るようにしましょう。寝る時には、部屋を暗くして布団に入ります。布団に入った後に、本を読んだりスマートフォンを見たりすると、眠れなくなることがあります。
Q7.前立腺肥大症を治療すると不眠症は良くなりますか?
はい、なかでも中途覚醒が良くなる場合があります。
体内の老廃物を含む尿は、いったん膀胱と呼ばれる袋に溜められて、尿道と呼ばれる管を通って体外へ出ます。一般的に、膀胱に尿が200mL前後溜まると、おしっこをしたいと感じて、トイレに行くことになります。
男性では、膀胱の出口である尿道を取り囲むように前立腺という臓器があります、前立腺は、歳をとると大きく固くなるため、尿道を周りからふさぐようになります。そのため、おしっこに行った後にも、うまく出しきれなかった尿が膀胱に残って(残尿)いるため、おしっこをしたはずなのに、すぐにおしっこに行きたくなります。そのため、夜中に何度も起きてトイレに行きますが、一回のおしっこの量は決して多くありません。夜中におしっこをしたいと感じて目が覚める回数(中途覚醒)が3回以上あり、目が覚めることが辛いと感じるのであればお薬による治療をお勧めします。ただし、その際、前立腺癌でないことを確認するための血液検査をすることをお勧めします。
Q8.睡眠時無呼吸症候群を治療すると不眠症は良くなりますか?
はい、なかでも中途覚醒と熟眠障害が良くなる場合があります。
睡眠時無呼吸症候群は、夜の寝ている間に呼吸が止まったり(無呼吸)弱くなったりする(低呼吸)ことによって、リラックスして寝ることができません。呼吸が止まると苦しくなり、夜中にたびたび目が覚めてしまったり(中途覚醒)、朝早く目が覚めてしまったり(早朝覚醒)、熟睡できなくなったりします(熟眠障害)。それによって、疲れが取れなかったり、日中に思いがけずうとうとしてしまったり、血圧が高くなったりすることがあります。
まず、疑わしければ検査をしてみることをお勧めします。睡眠時無呼吸症候群と診断がついても、根本的な治療法が無いことから、毎晩、夜間に呼吸を助けるため鼻(もしくは顔面)に特殊なマスクを着けて寝る必要があります。その装置を使用することによる不快感や金銭的負担によって、なかなか続けられない人もいます。ただし、お客さんを乗せる仕事(バスやタクシー運転手など)をしている患者さんでは、交通事故の原因になりますので、必ず治療を続けてもらう必要があります。
睡眠時無呼吸症候群についてもっと知りたい方は「睡眠時無呼吸症候群について」へ
Q9.レストレスレッグ症候群(むずむず脚症候群)とはどのような病気ですか?
夜間を中心に脚がむずむずするしてしまう病気です。
レストレッグ症候群は、昔はむずむず脚症候群と呼ばれ、夕方から夜中にかけて、両下肢に「むずむず」「かゆい」「じっとしていられない」などの症状が出て、眠れなくなってしまいます。脚を動かすことによって症状は消失するのですが、しばらくするとまた出現してきます。中年の女性でみられることが多く、鉄欠乏性貧血や腎臓病をわずらっている患者さんに合併しやすいと考えられています。
レストレッグ症候群は、睡眠薬での治療は難しく、一般的にパーキンソン病を治療する際に使うお薬によって治療します。ツノクリでもお薬を出すことはできますが、しっかりと治療するために専門医を受診することをお勧めしています。
Q10.お酒と睡眠薬を一緒に飲んでも良いですか?
お酒と睡眠薬の組み合わせは、絶対に駄目です。
お酒は酩酊状態を引き起こし、睡眠薬には脳の活発な活動性を抑える働きがあります。二つが同時に作用すると、より深い酩酊状態とより強い脳の活動性低下を引き起こし、記憶障害、呼吸抑制、熟眠障害、夜間の転倒外傷(ふらつき)などが起こることが知られています。特に、ベンゾジアゼピン系(→Q12)に属する睡眠薬は、肝臓で代謝(効き目を消失)されることから、同時にお酒が入ると、お薬の代謝がとどこおり、長くお薬が効いてしまいます。お酒と睡眠薬は相性の悪い組み合わせなのです。
Q11.睡眠薬を飲みたくないのでお酒で寝ても大丈夫ですか?
いいえ、駄目です。
お酒で眠ることは危険です。お酒は、酩酊状態となり入眠を促しますが、中途覚醒や早朝覚醒を引き起こして、総合的には睡眠の質を低下(熟眠障害)させます。さらに、お酒で眠ろうとして眠れない場合に、お酒の摂取量が増えてしまう傾向があります。眠れないことを理由に、お酒の量を増やすことを繰り返して、アルコール依存症になることもあります。眠ることができないのであれば、お酒に頼らず、ルールを守りながら睡眠薬を使用しましょう。
Q12.睡眠薬の中でも望ましい睡眠薬はありますか?
はい、あります。
現在、睡眠薬として① ベンゾジアゼピン系 ② 非ベンゾジアゼピン系 ③ メラトニン受容体作動薬 ④ オレキシン受容体拮抗薬が広く使用されており、比較的安全に使うことのできます。なかでも、ベンゾジアゼピン系睡眠薬を除く3種類は、6~12か月の長期的な安全性と有効性(睡眠薬としての効果を維持できる)が確認され、副作用も少ないことから、より望ましい睡眠薬とされています。
その内容に基づき、ツノクリでも、次のお薬を使用する場合が多いです。
- メラトニン受容体作動薬 ラメルテオン(ロゼレム)
- 非ベンゾジアゼピン系睡眠薬 ゾルピデム、エスゾピクロン(ルネスタ)
- オレキシン受容体拮抗薬 スボレキサント(ベルソムラ)、レンボレキサント(デエビゴ)
第6版 2024年10月06日