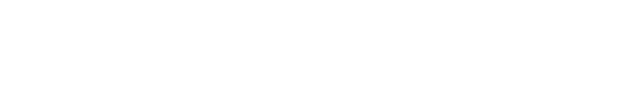排尿障害について
はじめに
おしっこに関する症状(排尿障害)は、若い人にはほとんどみられませんが、歳をとるにつれて増えてきます。排尿障害の原因のほとんどは、膀胱から尿道までのおしっこの通り道(下部尿路)のトラブルによって起こります。下部尿路の構造は男女で異なるため、排尿障害の症状や原因と治療も男女で大きく異なります。
男性の2大排尿障害は、おしっこの勢いが悪くなること(排尿遅延)と、夜間におしっこに行きたくなること(夜間頻尿)です。この排尿遅延と夜間頻尿を引き起こす原因のほとんどは、硬く、大きく硬くなった前立腺(前立腺肥大症(→Q16))です。そのため、大きく硬くなった前立腺を小さくもしくは柔らかくするお薬を利用して、おしっこを出やすくします。一方で、女性の2大排尿障害は、おしっこに行く回数が多くなること(頻尿)と、突然、尿意をもよおして我慢できなくなること(尿意切迫感)です。この頻尿と尿意切迫感を含む排尿障害を過活動膀胱(→Q14)と呼びます。過活動膀胱では、膀胱が硬くなり、膀胱内に十分な量の尿を溜めておくことが難しくなります。そのため、膀胱を柔らかくするお薬によって症状を緩和します。
ツノクリでは、排尿障害があっても、必ずしもお薬による治療が必要とは考えていません。ただ、排尿障害によって、十分な睡眠がとれなくなってしまったり、楽しみな外出を控えてしまったりすると、充実した生活を送ることが難しくなります。このように排尿障害によって生活の満足度が低下していれば、排尿障害を改善するためのお薬を使っても良いと考えています。ツノクリでは、まず、排尿障害について話を聞き、症状に合わせたお薬を提案します。もちろん、お薬による治療は、その原因だけでなく重症度によっても効果に違いが出るため、いくつかのお薬を試してもらうこともあります。ツノクリでは、皆さんにとって大切なことは、お薬を使うかどうかではなく、少しでも排尿障害が改善し、より充実した生活を送ることだと思っています。
主な排尿障害
蓄尿障害(しっかりと尿が溜められない)
「すぐにおしっこに行きたくなる」:頻尿(→Q6)
「突然おしっこに行きたくなり、我慢できなくなる」:尿意切迫感(→Q7)
「おしっこが漏れてしまう」:尿失禁(→Q8)
排尿症状(尿をするときに気になることがある)
「なかなかおしっこが出ない」:排尿遅延(→Q12)
「おしっこの勢いが弱い」:尿勢低下(→Q12)
「おなかに力を入れないとおしっこが出ない」:腹圧排尿(→Q12)
排尿後症状(尿をした後に気になることがある)
「おしっこが残っている感じがする」:残尿感(→Q13)
「おしっこをした後におしっこが漏れる」:排尿後尿滴下(→Q13)
Q1. 排尿障害とは何ですか?
下部尿路に原因のある、排尿に関わる症状のことです。
下部尿路とは、尿を貯める膀胱から尿道にかけての尿の通り道のことを指します。この下部尿路の解剖は、男女で大きく異なります。男性には、尿道の一部を取り囲むように前立腺(灰色)(→Q3)があり、陰茎があるため尿道(黄色)は17~18cmあり、途中で大きく曲がっています(イラスト参照)。一方、女性には、前立腺も陰茎も無いため、尿道(黄色)は3~4cm程度で、大きく曲がっている部分はありません(イラスト参照)。このような特徴から、男性には尿が出にくくなる症状が多く、女性には尿が出やすくなってしまう症状が多くなります。
Q2. 膀胱とは何ですか?
膀胱は腎臓で作られた尿を一時的に貯めておく臓器です。
腎臓で絶え間なく作られた尿は、尿管を通って膀胱に到達します。膀胱内に溜まる尿が、約200mLになると「おしっこをしたい」と感じるようになり、400mLを越えると「おしっこを我慢できない」と感じるようになります。
Q3. 前立腺とは何ですか?
前立腺は、男性のみが持つ臓器で、精液の働きを助ける作用があります。
前立腺は、男性のみにあり、膀胱から出てすぐの尿道を取り囲んでいます。前立腺は、アンドロゲンと呼ばれる男性ホルモンによって成長して、その機能が保たれ、精液を保護する前立腺液を作っています。年齢と共に大きくなり、60歳台では、男性の半数以上で前立腺の過度の肥大がみられ、前立腺肥大症(→Q16)と呼ばれる病気を引き起こします。
Q4. 下部尿路症状には主にどのような症状がありますか?
下部尿道症状は、主に、蓄尿症状(→Q5)、排尿症状(→Q12)、排尿後症状(→Q13)の3つに分けられます。
Q5. 蓄尿症状には主にどのような症状がありますか?
蓄尿症状は、主に、「すぐにおしっこに行きたくなる」頻尿(→Q6)、「突然おしっこに行きたくなり、我慢できなくなる」尿意切迫感(→Q7)、「おしっこが漏れてしまう」尿失禁(→Q8)の3つに分けられます。
Q6. 頻尿とはどのような症状ですか?
頻尿とは、1日に8回以上、おしっこに行く状態です。
一般的に、寝ている間におしっこに行くことは少ない(多くても1回程度)ですから、日中に8回以上おしっこに行くと頻尿と診断されます。頻尿は、おしっこによく行く時間帯によって、その原因を推測することができます。
おしっこに行く回数が、昼も夜も多く、合計8回以上あるの場合
昼夜問わずに、おしっこに行きたくなる人の多くは、膀胱が小さくなっています。膀胱は年齢と共に小さくなるため、一回に出るおしっこの量が少なくなり、代わりに、おしっこに行く回数が多くなります。
おしっこに行く回数が昼8回以上あり、夜1回以下の場合
昼だけおしっこに行きたくなる人の多くは、おしっこに関して心配な人(神経性頻尿)か、水分の摂取量が多い人(多飲)です。皆さんも、出かける前などにおしっこをしておいたほうが良いと考えると、おしっこをしないと気が済まなくなると思います。その気持ちが長く続いてしまうと、神経性頻尿になります。
おしっこに行く回数が夜2回以上あり、昼8回以下の場合(夜間頻尿)
夜だけおしっこに行きたくなる人の多くは、膀胱以外の下部尿路に障害がある人です。例えば、前立腺肥大症(→Q16)や過活動膀胱(→Q14)などです。他にも、不眠症や睡眠時無呼吸症候群が原因になることもあります。一方で、寝る前や夜間に起きた際に、水分を摂取することによって、おしっこに行きたくなることがあります。寝る前や夜間に水分を摂取して、寝ている間にトイレに行く回数が増えてしまう人は、寝る前と夜間の水分を控えることが大切です。
Q7. 尿意切迫感とはどのような症状ですか?
尿意切迫感とは、急におしっこをしたくなって、我慢できなくなってしまう状態です。
尿意切迫感は、事前に予期できずに、急におしっこをしたくなって、我慢できなくなってしまいます。そのため、長時間の外出などが難しくなります。このような尿意切迫感から、トイレに間に合わずに失禁してしまうとことを「切迫性尿失禁」(→Q9)と呼びます。
Q8. 尿失禁とはどのような症状ですか?
尿失禁とは、おしっこをしたくない時に、おしっこが出てしまう状態です。
尿失禁は、主に、「切迫性尿失禁」と「腹圧性尿失禁」(→Q9)、「溢流性尿失禁」(→Q10)、「機能性尿失禁」(→Q11)の3つに分けられます。
Q9. 切迫性尿失禁と腹圧性尿失禁(混合性尿失禁)とはどのような症状ですか?
主に、過活動膀胱や骨盤筋群のゆるみなどによって、女性に多く生じる失禁です。
頻尿(→Q6)で、尿意切迫感(→Q7)があり、かつ切迫性尿失禁を伴う場合に、過活動膀胱(→Q14)と呼ばれます。一方で、腹圧性尿失禁は、咳やくしゃみ、立ち上がった時などの腹圧がかかった際に、わずかに尿が漏れてしまう状態です。そして、切迫性尿失禁と腹圧性尿失禁の両方を持っている場合に、混合性尿失禁と呼ばれます。女性の失禁の内訳は、切迫性尿失禁:腹圧性尿失禁:混合性尿失禁が2:5:3とされています。これらは、過活動膀胱と骨盤筋群のゆるみによって生じます。切迫性尿失禁と腹圧性尿失禁(混合性尿失禁)は、過活動膀胱の行動療法(→Q15)によって改善することができます。
Q10. 溢流性(いつりゅうせい)尿失禁とはどのような症状ですか?
溢流性失禁は、残尿(膀胱に多くのおしっこが残る)ことによって、おしっこがあふれてしまう失禁です。主に、前立腺肥大(→16)によって生じる、男性に多い失禁です。
男性は、年齢と共に前立腺が大きくなるにつれ、残尿が増えてきます。増えすぎた残尿は、何らかの拍子にあふれ出てきます。そのため、溢流性尿失禁は腹圧性尿失禁(→Q9)に似ています。しかし、腹圧性尿失禁では、失禁のきっかけ(咳やくしゃみなど)がはっきりとしていますが、溢流性尿失禁では、意識せずに、それなりの尿が漏れ出てしまうことがあります。そのため、溢流性尿失禁では、夜間の失禁(おねしょ)がみられることがあります。溢流性尿失禁と腹圧性尿失禁は、排尿後の膀胱超音波検査で、残尿測定をすることにより判断することができます。
一方で、膀胱を収縮する力が弱くなることによっても溢流性尿失禁を生じることがあります。腰部脊柱管狭窄症、糖尿病性神経症、骨盤内手術後などでは、膀胱を収縮させる力を伝える神経に障害が起きることにより、残尿が増加して溢流性尿失禁をきたすことがあります。このような場合には、お薬による治療ではなかなか治りません。
Q11. 機能性尿失禁とはどのような症状ですか?
認知症や身体活動能力の低下によって生じる失禁です。
認知症では、当たり前と考える、「おしっこをトイレでしなければならない」という認識が低くなってしまう場合があります。そのため、おしっこに行かなかったり、ところかまわずおしっこをしてしまったりすることがあります。身体活動能力が低下してしまうと、上手にトイレでおしっこをすることが難しくなってしまいます。トイレでおしっこをする動作は、とても複雑なため、身体活動能力が低下すると、うまくこなすことが難しくなります。
どうしても上手におしっこができない場合には、感染症や床ずれの予防のためなどに、おむつによる管理が必要な場合があります。
Q12. 排尿症状にはどのようなものがありますか?
排尿症状には、排尿遅延、尿勢低下、腹圧排尿、および排尿終末滴下があります。
排尿症状は、さまざまな原因によって生じますが、多いのは前立腺肥大症(→Q16)です。前立腺肥大症では、尿道が圧迫されることにより、おしっこに時間がかかったり(排尿遅延)、おしっこの勢いが弱くなったり(尿勢低下)、お腹に力を入れないとおしっこが出なくなったり(腹圧排尿)、おしっこが尿道に残ってしまい(排尿終末滴下)パンツを汚してしまったりすることがあります。もちろん、このような症状は、他の病気でも見られることがあります。
Q13. 排尿後症状にはどのようなものがありますか?
排尿後症状は、主に残尿感のことを指します。
残尿感とは、おしっこをしたのに、おしっこが残っているような感じがすることです。実際には、膀胱内におしっこが多く残っていることも、膀胱内におしっこが残っていないこともあります。これらは、排尿後の膀胱超音波検査で、残尿測定をすることにより判断することができます。膀胱内におしっこが残っている残尿感には、前立腺肥大症(→Q16)や腰部脊柱管狭窄症などがあり、膀胱内におしっこが残っていない残尿感には、膀胱炎や間質性膀胱炎などがあります。
長期にわたる残尿感は、男性に多く、そのほとんどが前立腺肥大症(→Q16)です。一方、突然始まった残尿感は、女性に多く、そのほとんどが下部尿路感染症(膀胱炎)です。
Q14. 過活動膀胱とはどのような病気ですか?
過活動膀胱は、 頻尿(→Q6)と尿意切迫感(→Q7)と切迫性尿失禁(→Q9)の3つの症状を持ち合わせる症候群です。
過活動膀胱は、病気の名前ですが、実際は、下部尿路障害の3つの症状がある人たちのことを指します。本邦の、過活動膀胱患者数は、1,000万人程度と推定されていますが、治療している人は10~20%程度に過ぎません。3つの症状の中でも、特に、(切迫性尿失禁を含む)尿意切迫感が重要です。男性では、前立腺肥大症(→Q16)により過活動膀胱をきたし、女性は、複数の原因が合わさって過活動膀胱をきたします。
過活動膀胱は、主に、筋肉訓練(行動療法)とお薬による2種類の治療方法があります。行動療法(→Q15)では、下部尿路を支える骨盤底筋群を鍛えて、おしっこをするのを我慢し、それを繰り返します。お薬による治療では、膀胱の緊張を抑えることによって、おしっこに行きたくなる気分を先延ばしにします。具体的には、抗コリン薬かβ3作動薬、もしくはその両方を使います。抗コリン薬は、のどが渇く感じや便秘などの副作用があり、β3作動薬ではそれらの副作用は少なくなります。
ツノクリでは、主に、抗コリン薬としてソリフェナシンを使い、効き目が弱い、もしくは副作用などが出た場合に、β3作動薬としてミラベグロン(ベタニス)を使っています。
Q15. 過活動膀胱の行動療法とはどのような治療ですか?
過活動膀胱の行動療法は、骨盤底筋群を鍛える筋力訓練です
過活動膀胱では、骨盤底筋群のゆるみから、(切迫性尿失禁を含む)尿意切迫感が生じることが分かっています。特に女性では、出産や骨盤内手術などで骨盤底筋群がゆるむことがあり、尿意切迫感の改善に骨盤底筋群の訓練が効果的です。いくつかの方法がありますが、お尻の穴をキュッと閉じることを意識する運動を、1日100回ぐらい繰り返すことが大切です。1か月間ほどで効果が出るとされています。1か月で効果が出なくても、2-3か月続けると効果が出る人もいます。ユニ・チャームのホームページでは「骨盤底筋トレーニング」の動画を見ることができますので、参考にしてみて下さい。さらに、おしっこに行きたいときに、キュッと(お尻の穴を閉じる要領で)5秒間ほど尿道を締めます。おしっこに行きたいという気持ちを意識せず、5~10分ほどおしっこに行くのを我慢します。これを繰り返すことによって、徐々におしっこを我慢できる時間が増え、最終的には2~3時間おしっこを我慢できるようになります。過活動膀胱の行動療法は、腹圧性尿失禁にも効果があります。
Q16. 前立腺肥大症とはどのような病気ですか?
前立腺(→Q3)が大きくなりすぎることで、尿道が狭くなり、さまざまな下部尿路症状をきたす病気です。
前立腺は、男性ホルモンにより年齢と共に大きくなります。60歳台の男性の半数以上には、なんらかの下部尿路症状が出現します。なかでも、前立腺肥大症は、高齢男性の夜間頻尿と尿意切迫感の主な原因です。
前立腺肥大症の治療には、前立腺を小さく柔らかくするお薬を使います。一般的なクリニックでは、前立腺内の尿道を通りやすくしてくれるα1遮断薬や、前立腺を小さく柔らかくして尿道を通りやすくし、さらに膀胱の蓄尿量を増やしてくれる5α還元酵素阻害薬を使います。いずれのお薬も、副作用として精力減退がみられることがあります。また、α1遮断薬では起立性低血圧が、5α還元酵素阻害薬では乳房の疼痛などが出現することがあります。さらに、泌尿器科専門クリニックでは尿道や前立腺の筋肉を柔らかくしてくれるPDE5阻害薬を使う場合もあります。もちろん、物理的に尿道を通りやすくする、前立腺肥大症の手術が最も効果的な治療法です。一方で、前立腺肥大症の患者さんの中には、前立腺がん(→Q17)を合併している場合があります。そのため、ツノクリでは、前立腺肥大症が疑われる患者さんは、定期的な血液検査(前立腺がんの腫瘍マーカーである好感度PSA値の確認)をお勧めしています。
ツノクリでは、主に、α1遮断薬としてタムスロシン(ハルナール)やシロドシン(ユリーフ)を使い、効果が弱い、もしくは副作用が出た場合に、5α還元酵素阻害薬としてデュタステリド(アボルブ)を使います。PDE5阻害薬であるタダラフィル(ザルティア)は、EDのお薬としても利用されているため、若い男性の前立腺肥大症に有効です。ただし、若い男性の前立腺肥大症は、治療期間が長くなるなどの理由から、泌尿器専門のクリニックでの治療をお勧めしています。さらに、PDF5阻害薬は、ED治療薬として使用された際に、心筋梗塞、心臓突然死、および脳出血などの、重篤な心血管系疾患を増加させたとの報告があります。そのため、動脈硬化性疾患をきたすような生活習慣病を持つ患者さんが使う際には、特に注意が必要です。
Q17. 前立腺がんはどのような病気ですか?
前立腺がんは、前立腺に生じるがんです。
前立腺がんは、高齢者に発症する場合が多く、90%以上が60歳以上の男性です。前立腺がんは、一般的に進行が遅く、症状がみられない場合も多いことから、発見までに数年間かかることが少なくありません。また、前立腺がんは骨に転移しやすいことから、腰痛や骨折などで発見される場合もあります。
ツノクリでは、排尿障害を持つ高齢男性だけでなく、市区町村の健康診断を受ける60歳以上の男性にも、前立腺がんのスクリーニング検査(前立腺がんの腫瘍マーカーであるPSA値の測定)を受けることをお勧めしています。前立腺がんのスクリーニング検査は、血液検査のため、特殊な機器や準備などは必要ありません。もちろん、前立腺がんが疑われれば保険診療でも検査をすることができます。
第二版 2024年11月03日